
私が公務員になったのは、もう40年も前のことになります。
私が合格した公務員試験
・川崎市役所(上級)
・国家公務員(中級)
・裁判所事務(中級)
・東京都職員(中級)
・特別区職員(中級)
勉強方法は不変だと思いますので、私のかつて行った勉強方法をお話しします。
公務員になってから自己啓発の意味もあって取得した資格試験(司法書士)でも同じような勉強方法でした。
教材
当時は現在のように、書店では公務員受験の参考書は売っていませんでした。
今では店頭に様々なタイトルの本が並んでおり、その華やかさに目を奪われてしまいます。
しかし、出版されている参考書や過去問集などは思ったほどには体系的ではなく、出版社が運営している通信教育もしくは講座へ誘導する内容のモノも多く見受けられます。
私が取ったのは「実務教育出版」の「公務員講座」でした。
たしか「国家上級」「国家中級」「地方上級」「地方中級」などに分かれていたと思います。
この中から私は「地方上級」の行政職を受講しました。
今のようにオンラインはなく、テキストと問題集、論文などの通信添削がついたもので、独学に近い講座でした。
今、考えると多くの人は脱落していったように思われます。
勉強方法
試験範囲の科目に比べてテキストは薄く、最初見た時は「これで受かるのか」と不安に思ったものでした。
テキストの通読
しかし、私は「やるしかない」という気持ちしかなく、最初はテキストを通読しました。
私は法学部に在籍していたので、法律分野は優しく感じましたが、法律分野は一つも落としてはならないと心に決めました。
その他の科目は、「理解よりも記憶」を重視しました。
チンプンカンプンの科目もありましたが、講座のテキストと問題集に掲載されている事項は完ぺきに頭に刷り込みました。
テキストは2、3回通読したと思います。
テキスト+問題集
次にテキストを読んで、問題集を解きました。
問題集で間違えた個所は、必ずテキストに戻って復習しました。
しかし、テキストに載っていない問題もありました。
その問題は、ルーズリーフをテキストの該当のページに挟み込み、ルーズリーフに書き込んでいきました。
オリジナルテキスト
ルーズリーフを挟むページが思ったよりも多くなり、最初のテキストより厚いオリジナルテキストの完成です。
このオリジナルテキストの内容は、試験日当日まで忘れないように何度も何度も読みこんだものです。
勉強範囲を広げない
私にとって、この方法で最初に挙げた公務員試験全てに合格することができました。
公務員講座の他にはまったく手を広げませんでした。
朝は9時から夕方5時まで地元の公立図書館で勉強しました。
昼食は同じ建物にある定食屋さんでオムライスを食べるのが常でした。
勉強は気合を入れましたが、昼食後は眠いです。
本来ならいけないことだと思いますが、図書館の方の目を盗んで居眠りもしました。
大学受験より勉強したと思います。
基礎を大切にするのは他の資格試験も同じ
私は公務員になってからも資格試験にチャレンジしました。
どの試験もやり方は同じです。
範囲を広げず、講座を信じて繰り返しこなす。
これでほぼ多くの資格をとることができます。
最後に
公務員試験で「倍率」が公表されます。
私は全く気にしませんでした。
公務員になってからも「今年は倍率が高いんだってよ」という声が聞こえてきましたが、合格に必要な実力とは全く関係ないと思います。
なぜなら、試し受験の人が多いからです。
公務員試験は難しい試験だとは思いません。
でも、勉強せずには合格しません。
勉強せずに受かれば儲けものという受験生が多いのは事実です。
私も多くの「試し受験」の同級生が落ちているのを見てきました。
地道に繰り返し勉強法をとれば必ず合格できる。
私はそう信じて疑いません。
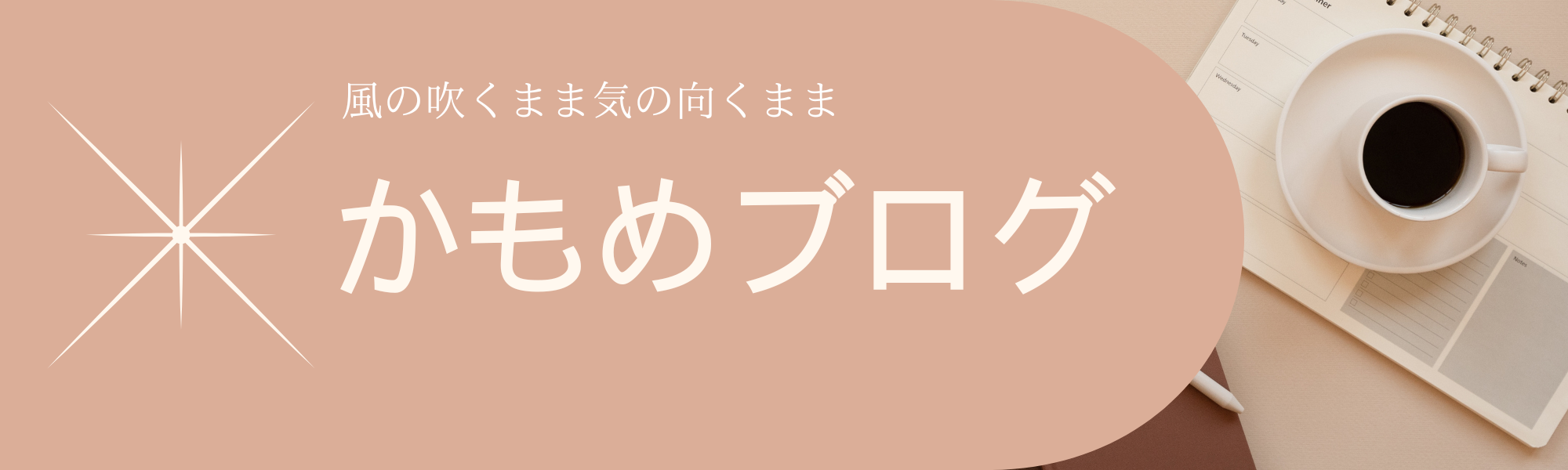
コメント